見えない支配に、名前をつける──『空気という名の組織支配』シリーズ 3/15
「また今年も同じ内容です」
そう聞いた瞬間、心のどこかで「ああ、今年もか…」と小さくため息が出る。でも不思議なことに、それに異を唱える人はいない。むしろ、変えようとする人の方が“空気を読まない存在”として警戒される。
本来は「必要だから続ける」はずだった行事や制度が、いつのまにか「続けるために存在するもの」になってしまう。そしてその構造の中で、変化を望む声は疲弊し、やがて沈黙していく。
今回は、「なぜ“不満があるのに続けてしまう”のか?」その根本の仕組みに迫ってみたい
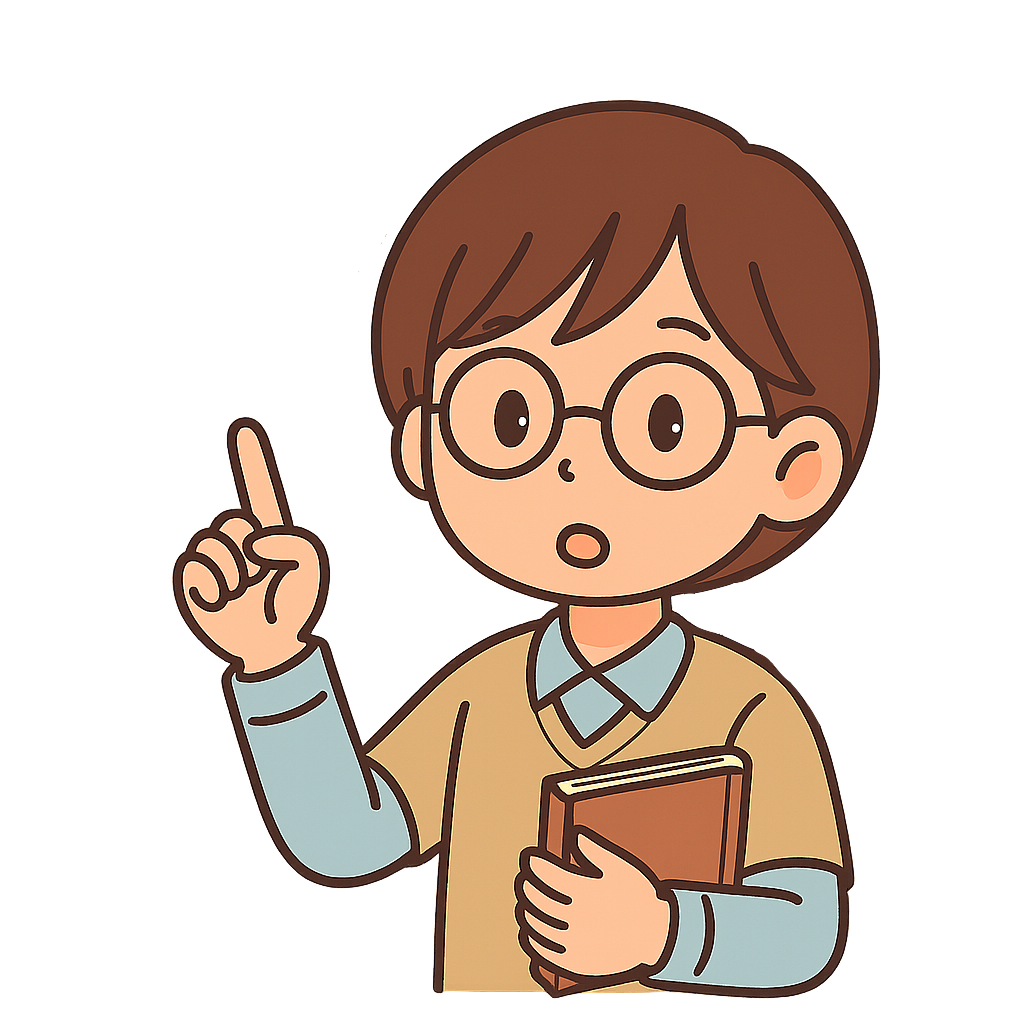
カクトくん
なんかさ…なんで、みんな不満あるのに“去年と同じ”をそのまま続けるんだろう?誰かが「これって意味あるの?」って言っても、結局やるじゃん。

ヨミノ博士
ふむ…それは、“変えること”にだけ重い責任が課され、“変えないこと”が無条件に守られているからかもしれないね。

ミツキさん
あるある。PTAの行事とかそうじゃん。「去年こうだったから」で、そのままやる。改善しようとすると「余計なことしないで」って空気になるの、ホントしんどい。

キクネさん
消防団の操法大会もそうです。「誰も出たがらないのに、隣の分団が出るからうちも出るしかない」って。やめたらやめたで“説明が大変になる”って。

ヨミノ博士
なるほど。“変える側”にはリスクと説明責任が発生する。でも“去年と同じ”を選ぶと、それらはすべて回避できる──それが“継続の免罪符”という構造だ。
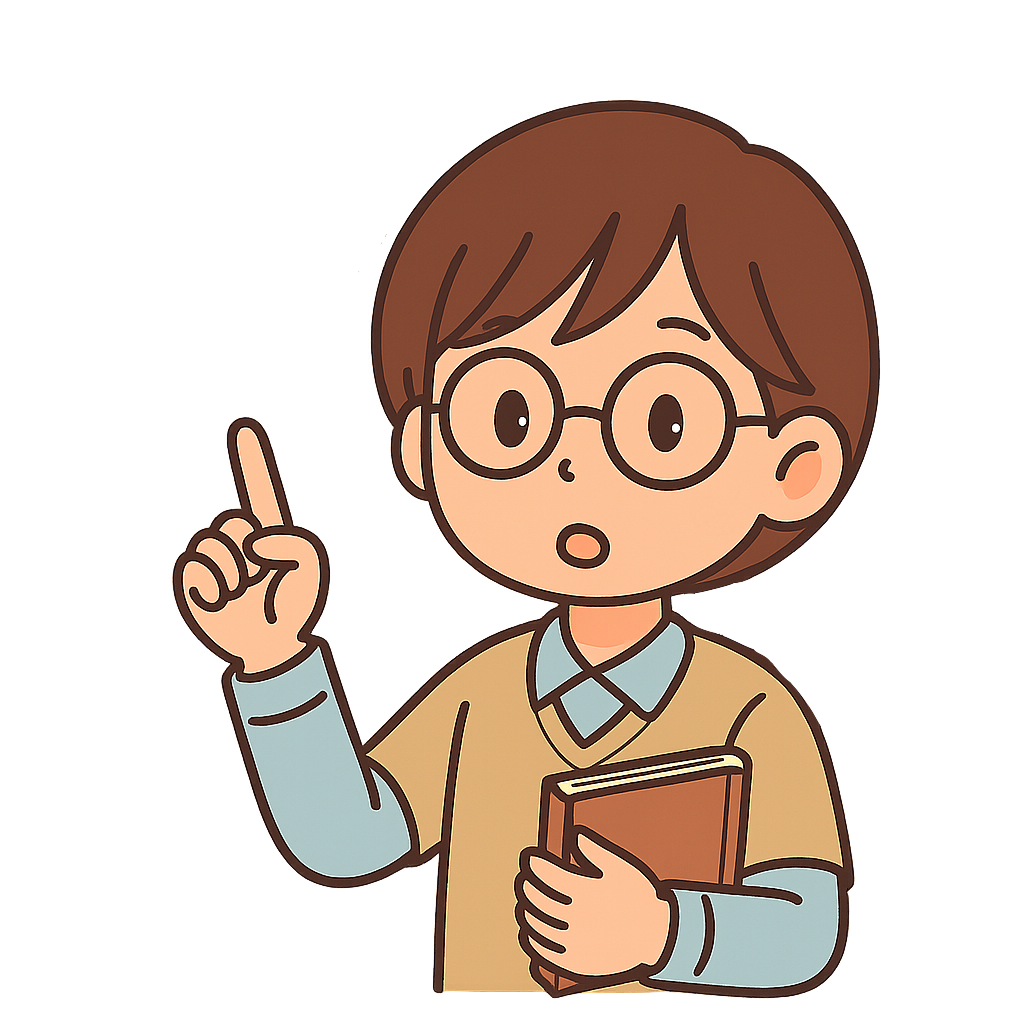
カクトくん
あー、なんか…変えたら“お前のせい”になるのに、続けたら“誰のせいでもない”って感じだよね。

ミツキさん
そうそう!失敗しても「前例通りでした」で通っちゃう。でも新しいことしてミスったら“余計なことした”って言われる。そりゃ変えたくなくなるわ。

キクネさん
うちの市役所も、何か変えようとすると「前にやったことある?」って聞かれます。で、前例なければ“要検討”…で終わる。

ヨミノ博士
“何もしない”が最適解に見える構造──それは変化を拒む力ではなく、“変わらないことが楽すぎる”という無言の誘導だ。
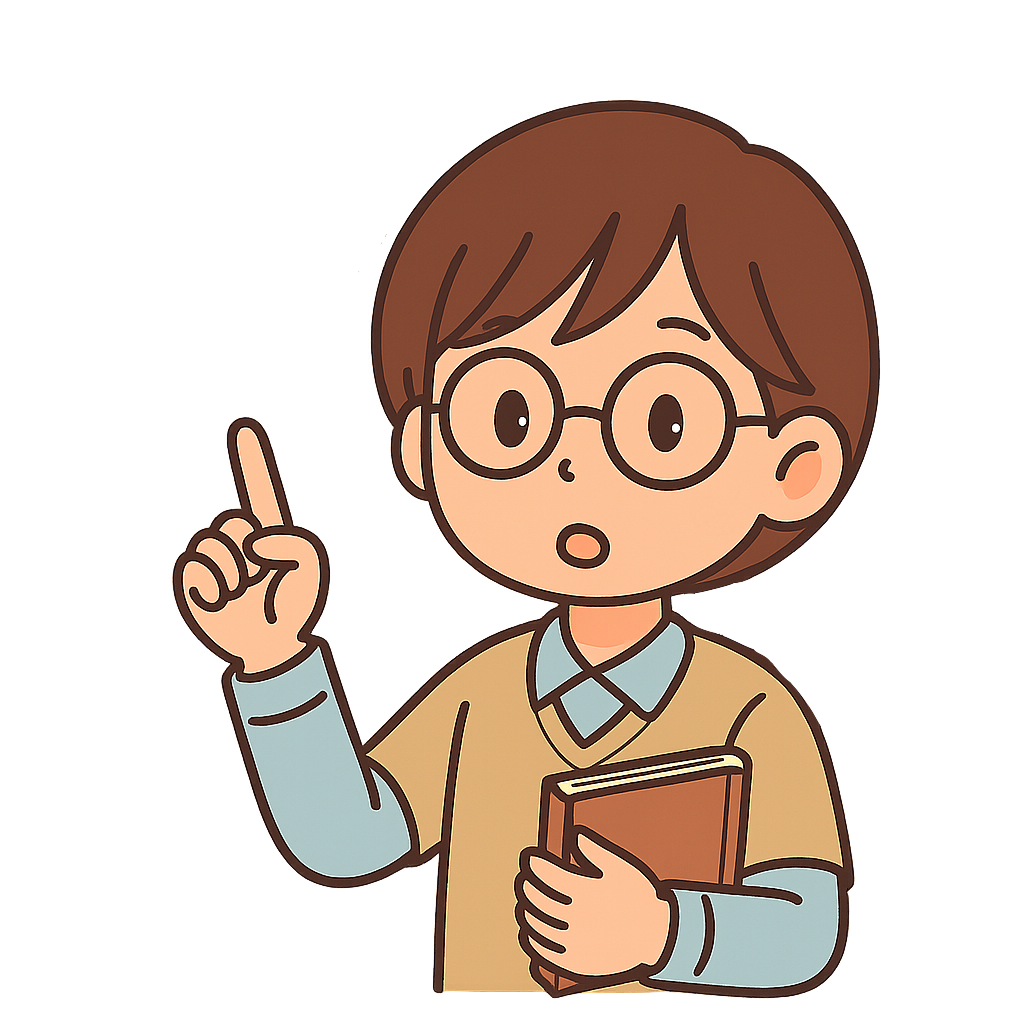
カクトくん
なんかさ…考えれば考えるほど、あれってもう“変えられない仕組み”になってる気がしてきた。

ヨミノ博士
ならば、そろそろこの仕組みに名前をつけよう。名前を持てば、見えない壁にも問いを立てられるからね。
違和感のおさらい
1つ目:「変えたい人」だけが責任と説明コストを負う構造
PTAや消防団のような地域組織では、「変える」ことには多大な説明が求められ、失敗すれば“お前のせい”になる。一方で、「去年と同じ」には何の説明もいらず、誰も責められない。この非対称性が、“変えること”をためらわせる空気をつくっている。
2つ目:「変えないこと」が異常に守られ、最も安全な選択になっている
形式を踏襲するだけで“無難”とされ、実質的な効果や目的が問われない。何もせず従う人が“ありがたい存在”になり、「何もしないこと」が最適化される仕組みができあがっている。
3つ目:全体が沈んでいても、誰の責任にもならない安心構造
失敗のリスクは個人に、衰退のリスクは全体に分散される。だから誰も動かず、気づかないうちに「変わらなさ」そのものが組織の限界をつくってしまう。
この3つが重なることで──
「誰も悪くないのに、確実に沈んでいく構造」が完成している。
“何もしない”が最も守られ、“変えようとすること”が損になる空気は、見えないまま組織を蝕んでいく。
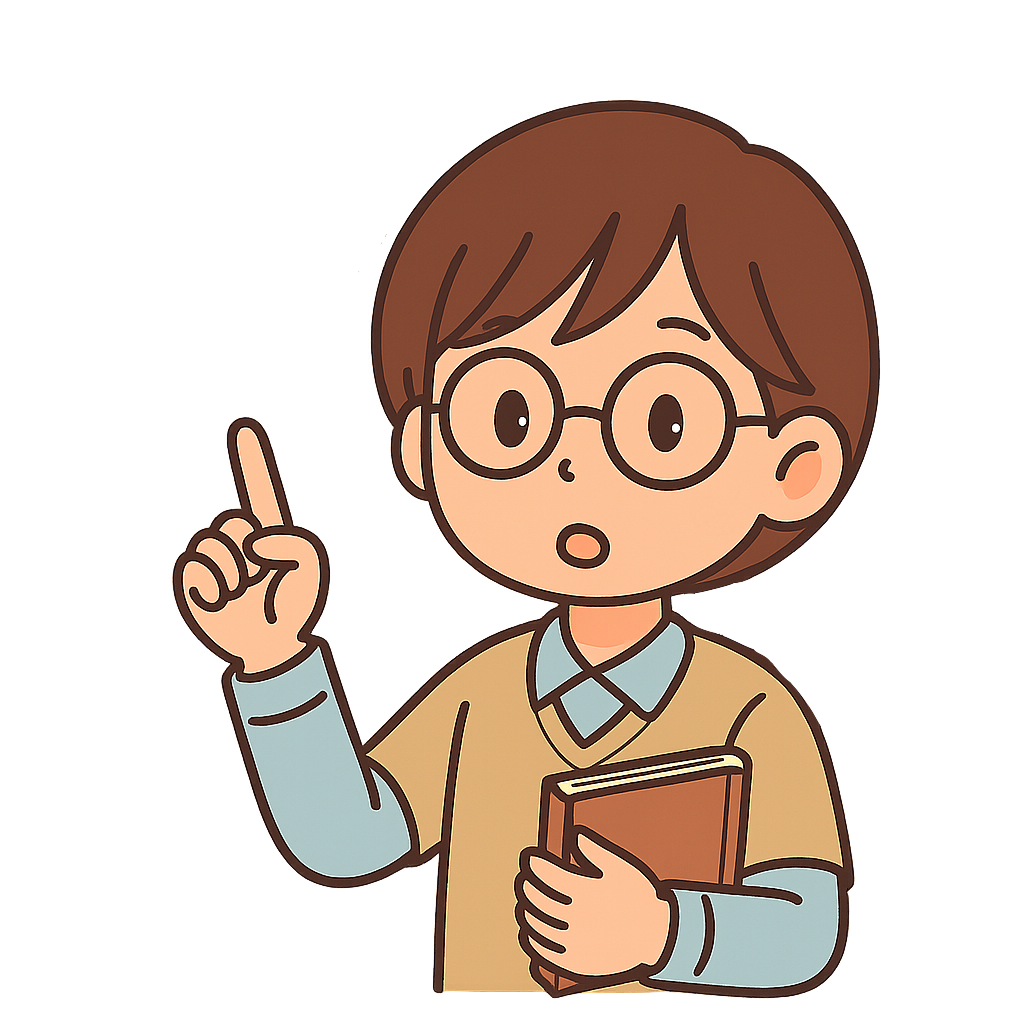
カクトくん
この感覚、ちゃんと名前をつけたいな。“変えようとすると責められて、何もしないと守られる”っていう、あの空気…

ヨミノ博士
ならば、こう呼んでみるのはどうだろう──「継続の免罪符」。
“去年と同じ”というだけで、あらゆる疑問や責任から逃れられる構造を表す言葉だよ。

ミツキさん
いや、もっとズバッと言いたい。“繰り返すだけで正義”になるって、それもう呪いじゃん。
なんなら「去年至上主義」とか、どう?

キクネさん
……あ、でもそれって、「変えないことが心理的に楽」ってだけじゃなくて、
“前例があるから”で全部止まるあの感じ、ありますよね。
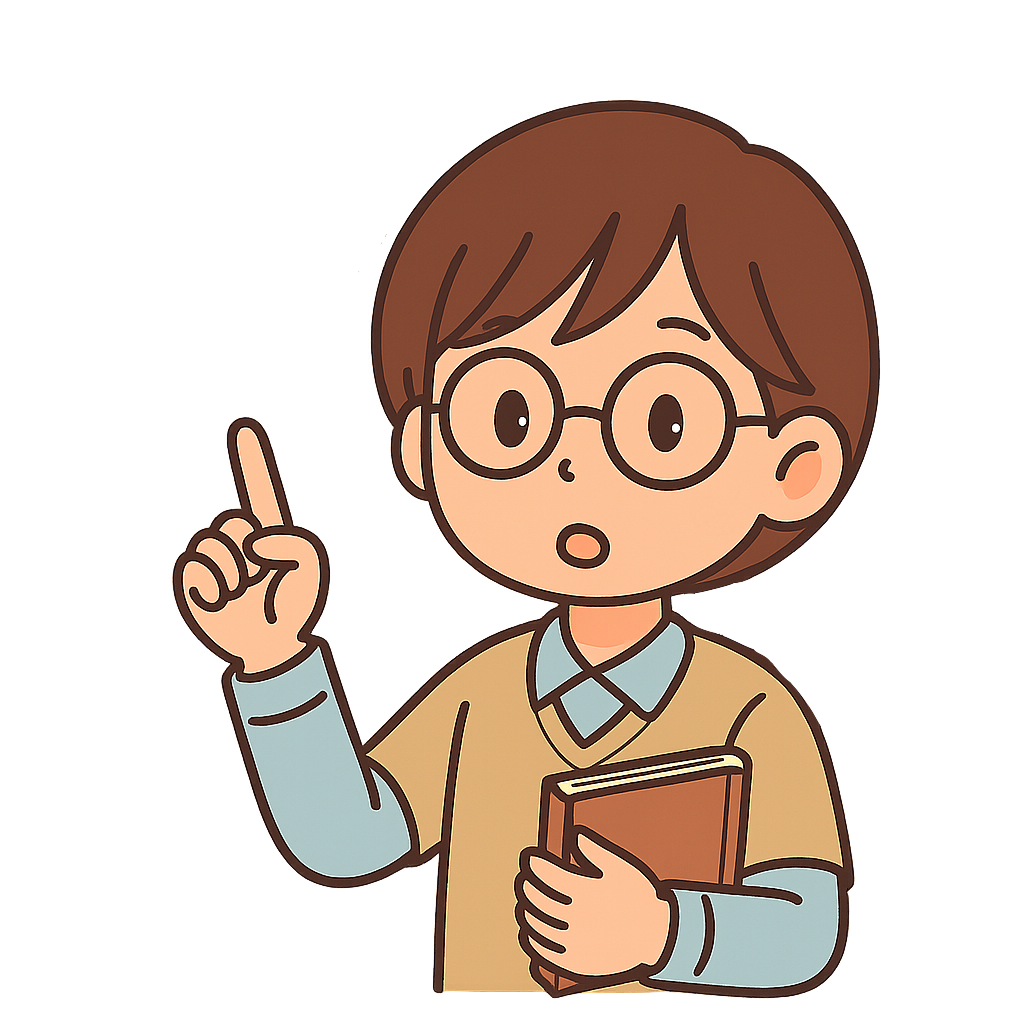
カクトくん
うんうん。あれって、「不安だから変えない」ってより「前例があるから安心」っていう…なんか別の力が働いてる気がする。

ヨミノ博士
では、それを明確に言葉にしよう。
“現状維持バイアス”を、さらに日本的に具体化した構造として──
私はこれを「前例維持バイアス」と名づけようと思う。
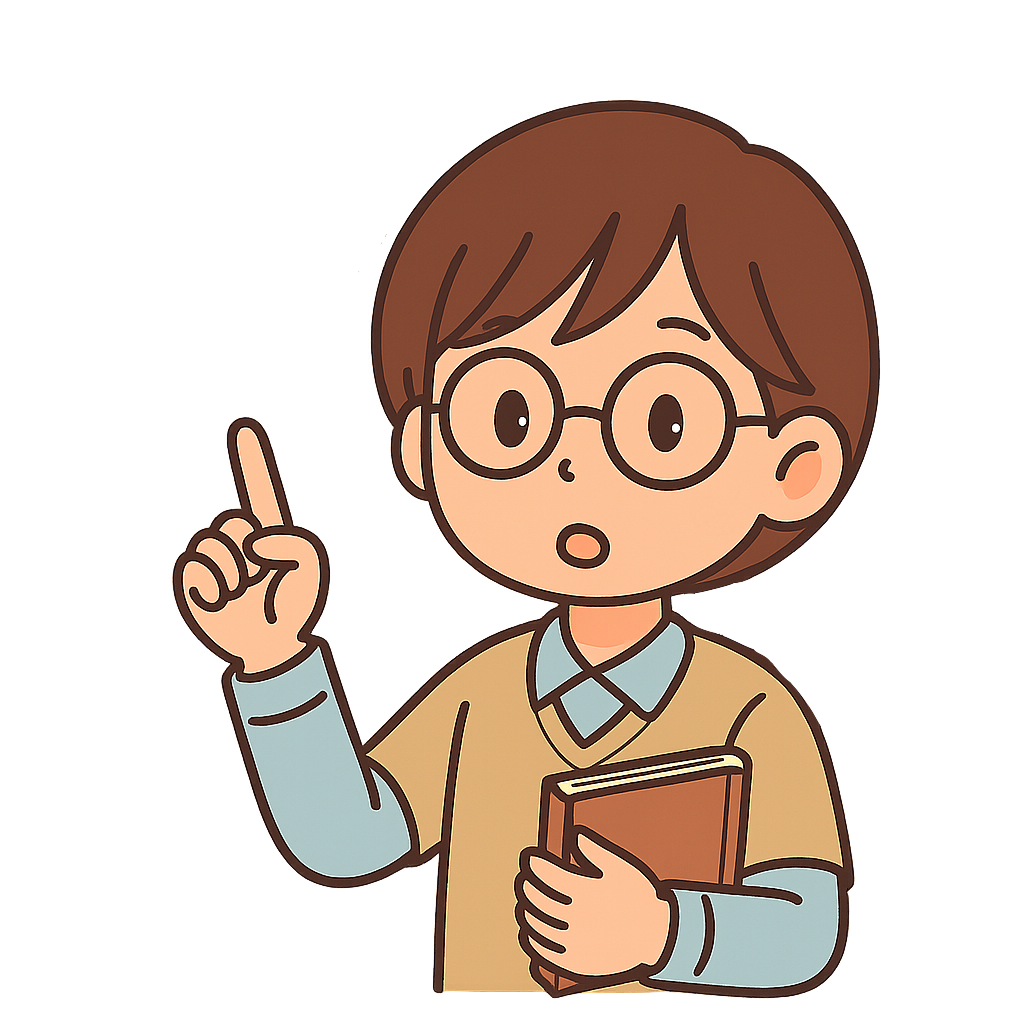
カクトくん
博士、それです!
“前例がある”ってだけで、全部が止まる空気──まさにその名前がぴったり。
まとめ
本当は「やめたい」「見直したい」と思っている。
なのに誰も声を上げず、“去年と同じ”がそのまま続いていく。
なぜか──そこには、「変えようとする者にだけ責任が降りかかり、何もしない者が最も守られる」という構造がある。
声を出すことが“損”になり、沈黙が評価される環境では、変化は淘汰され、組織は静かに沈んでいく。その見えない壁に私たちは名前をつけた。
──「前例維持バイアス」
問いを立てることすらリスクになる空気の正体。
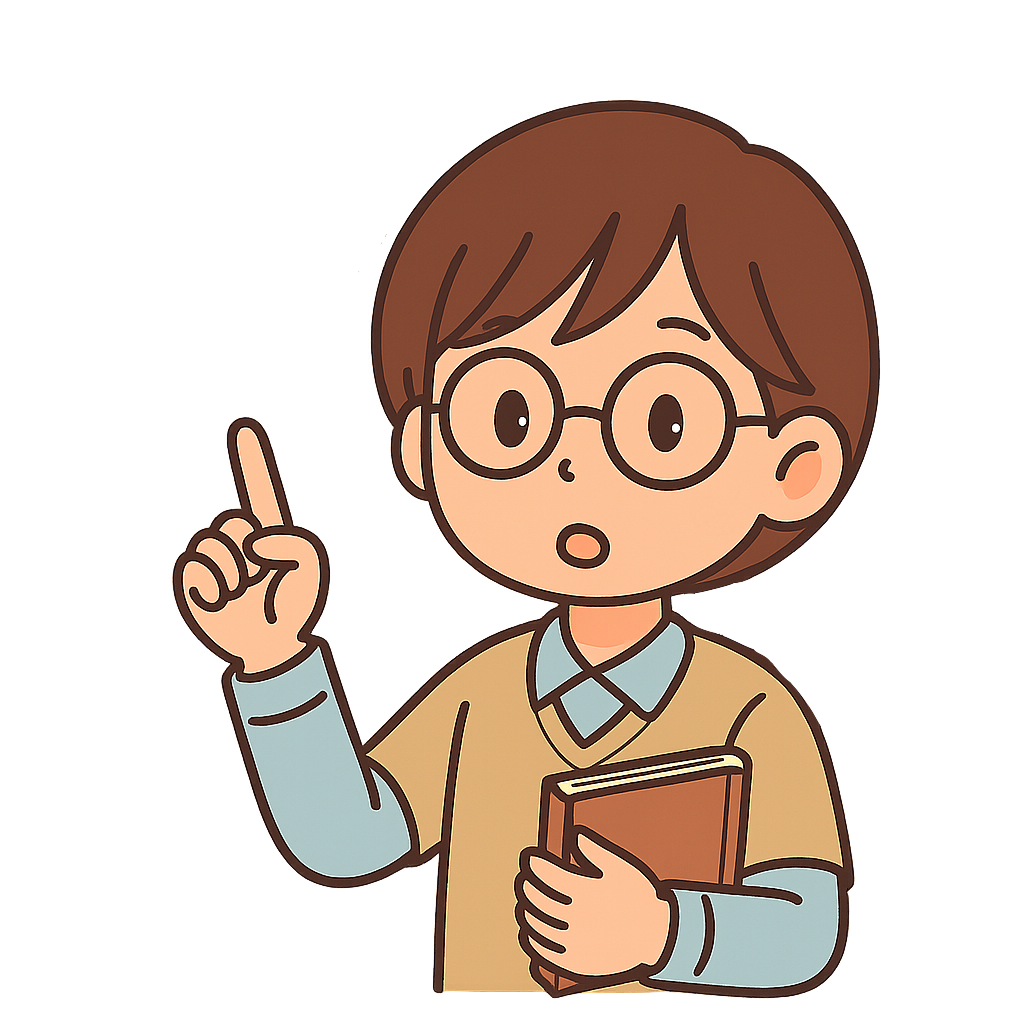
カクトくん
博士って…なんでそんなに“空気の裏側”が見えるんですか?

ヨミノ博士
それはね、私は“人より構造に敏感”だからだよ。空の上から町を眺めるように、物事を見ているんだ。
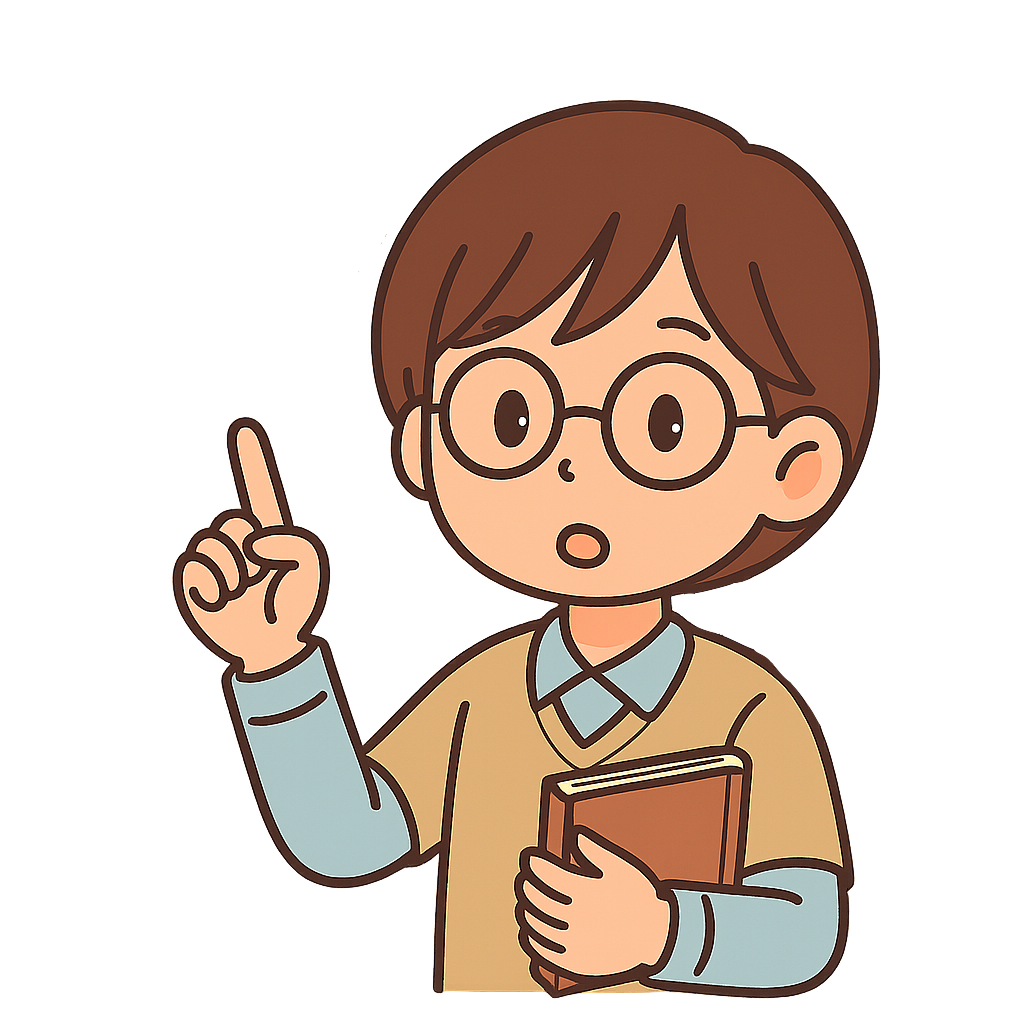
カクトくん
たしかに…僕らが感じてるのは空気とか感情なのに、博士はいつも“仕組み”で話す。

ヨミノ博士
感情はヒントになる。でも、構造を言葉にできたとき、それはただの違和感じゃなく“問い”になるんだよ。

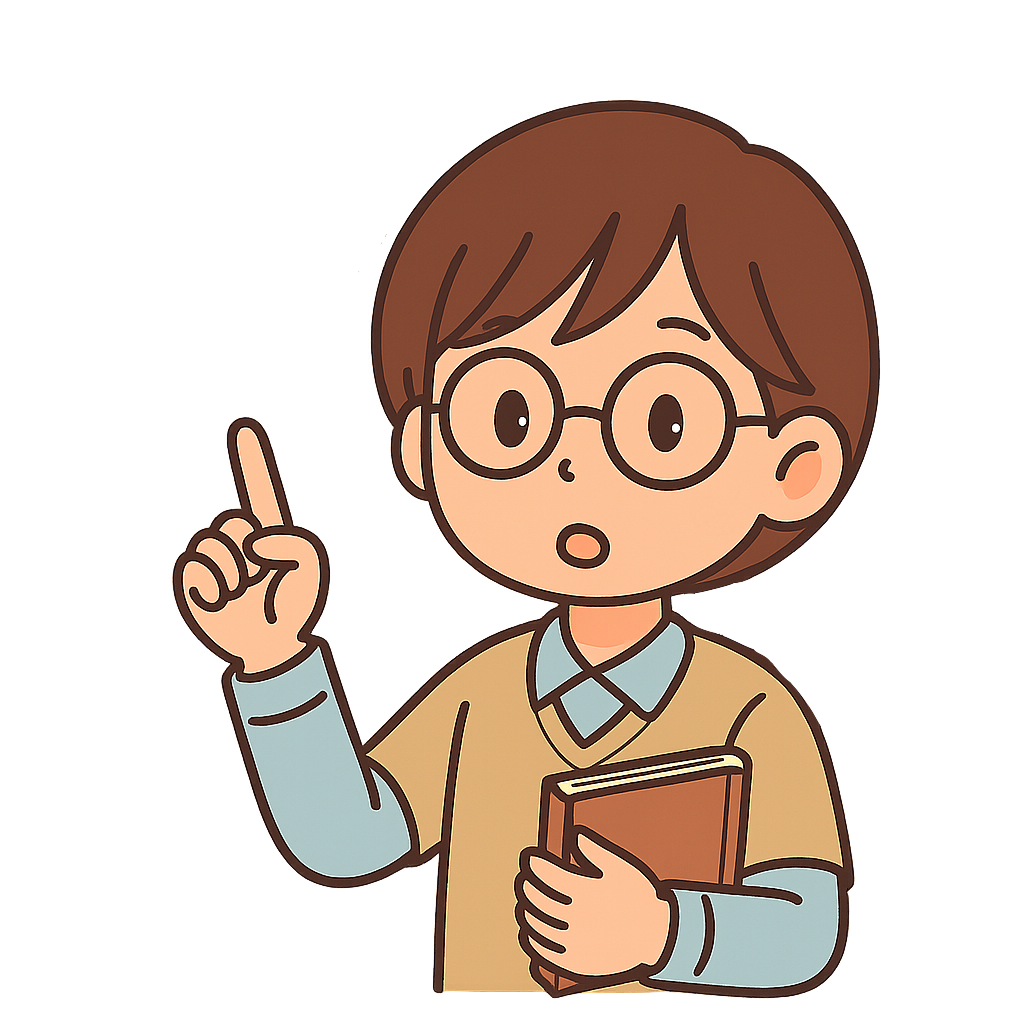




コメント